
第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件弁護士アトム」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。
アトムは夜間土日も受け付けの相談窓口で刑事事件のお悩みにスピーディーに対応いたします。
保釈の条件とは?保釈金の相場、条件違反はどうなる?
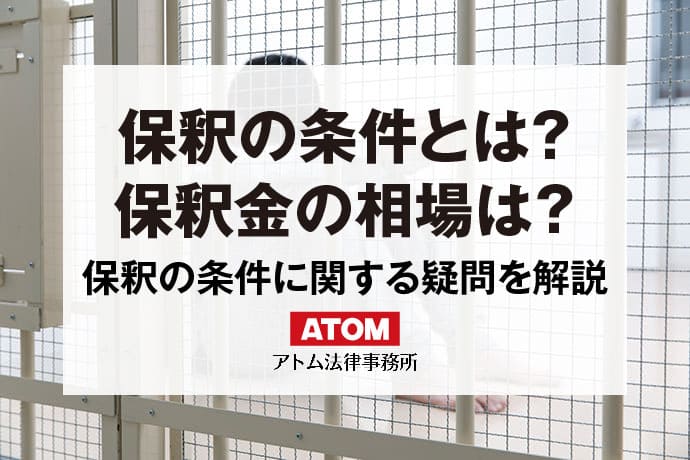
- 保釈の条件って、どんな条件があるの?
- 保釈の条件として、保釈金はいくら必要?
- 保釈の条件違反はどうなるの?
保釈には、いろいろな条件があります。
許可の条件、保釈保証金や身元引受人の確保、保釈中に守る条件などなど沢山あります。
しかしいま保釈についてお悩みの方は、保釈の条件をクリアできるのか、とくに重要な条件は何なのか、保釈の条件に違反したらペナルティがあるのかなどよく分からないことが多く不安になることかと思います。
この記事では、こういった保釈の条件に関する疑問について、徹底解説していきます。
おすすめ
アトム法律事務所では「初回接見出張サービス」を行っています。まずは何があったかを本人に確かめてきてほしい、家族は味方であると伝えたいといった方のお問い合わせが多く、正式契約前でも利用できます。最短当日に対応可能な場合もあるので、お早めにご連絡ください。
 刑事事件でお困りの方へ
刑事事件でお困りの方へ
ご希望される方はこちら
目次
保釈の許可をもらうための条件とは?
権利保釈の条件は?
一定の事由に該当しない場合、保釈請求が必ず許可されるというのが、権利保釈(必要的保釈)です。
権利保釈の条件については、次のような条文があります(刑事訴訟法89条)。
この条文にある6つの条件(保釈除外事由)に該当しなければ、保釈請求をしたら、必ず保釈は許可されます。
保釈の請求があつたときは、次の場合を除いては、これを許さなければならない。
刑事訴訟法89条
- 被告人が死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。
- 被告人が前に死刑又は無期若しくは長期十年を超える懲役若しくは禁錮に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき。
- 被告人が常習として長期三年以上の懲役又は禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。
- 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
- 被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき。
- 被告人の氏名又は住居が分からないとき。
このような1~6までの条件について、ひとつずつ解説していきます。
1.一定以上の犯罪を犯していないこと
一つ目の事由は、「一定以上の犯罪を犯していないこと」です。
一定以上の犯罪というのは、「死刑、無期懲役、短期が1年以上の有期懲役や禁錮」にあたる罪です。
2.今までに一定以上の犯罪を犯していないこと
二つ目の事由は、「今までに一定以上の罪を犯していないこと」です。「以前に、死刑、無期懲役、長期が10年を超える懲役や禁錮にあたる罪を犯していないこと」が条件です。

弁護士
具体的には「傷害罪」「強盗罪」などの罪について、有罪判決を受けていないというのが条件となります。
3.常習性がないこと
三つ目の事由は、「常習性がないこと」です。すなわち、「上限が3年以上の懲役や禁錮にあたる罪について、くり返していないこと」が条件です。

弁護士
具体的には「窃盗罪」「詐欺罪」などの罪について、常習として犯していないということが条件となります。
4.証拠隠滅のおそれがないこと
四つ目の事由は、「証拠隠滅のおそれがないこと」です。

弁護士
実務では、多くの場合、事件を否認しているだけで証拠隠滅のおそれがあると疑われてしまいます。
否認事件の場合は、保釈が認められにくくなるでしょう。
5.被害者などに危害を加えないこと
五つ目の事由は、「被害者などに危害を加えないこと」です。
「被告人は、被害者などに「お礼参り」に行く可能性がある」というふうに判断されると、被告人は保釈してもらえません。
「お礼参り」というのは、被害者・告発者・裁判で不利な証言をするような者などに対して、報復行為をすることを意味します。

弁護士
たとえば、「事件について反省していること」「被害者に対して謝罪していること」等を根拠を持って証拠として提出できれば、保釈の可能性は高まります。
6.名前と住所が分かること
六つ目の事由は、「名前と住所が分かること」です。
氏名や住居が分からないと、逃亡のおそれがあるから保釈できないと考えられてしまいます。
実務上、権利保釈が認められるケースは少ない
いままで見てきた1~6の事由のどれかに該当しない場合、被告人は、権利保釈が許可されます。
しかし、実際のところは、裁判所が権利保釈を認めるケースはあまり多くありません。
特に「証拠隠滅のおそれがないこと」「被害者などに危害を加えないこと」が認められない場合が多いです。

弁護士
権利保釈は、被告人が事件を否認しているだけで認められにくくなることがあります。
否認することで、裁判所は「被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由」があると簡単に認めてしまいます。
ですが、権利保釈の除外事由に該当する場合でも、ほかの種類の保釈が認められることはあります。
実務では、後述する裁量保釈を目指すことも多いです。
裁量保釈の条件は?
裁量保釈(任意的保釈)は、裁判官の裁量で決められる保釈です。
権利保釈が認められなくても、「裁量保釈」という保釈の許可を目指すことは可能です。
裁量保釈の条件については、次のような条文があります。
裁判所は、適当と認めるときは、職権で保釈を許すことができる。
刑事訴訟法 第90条
要するに、裁量保釈の条件は、裁判所が適当と認めるかどうかによります。つまり、裁量保釈を得るには、裁判官を説得することが条件です。

弁護士
裁量保釈を請求する場合は、保釈の「相当性」と「必要性」を、裁判所に訴えます。
「相当性」とは、「保釈請求がどれだけ妥当であるか」をいいます。具体的には「逃亡や証拠隠滅のおそれがないこと」を主張します。
「必要性」とは、「保釈による身柄の釈放がどれだけ必要であるか」をいいます。
具体的には「被告人を保釈しなければ困る事情があること」を主張します。
例えば「一家の大黒柱である被告人が勾留されることで、収入が途絶えて一家が経済的に困窮する」「経営者である被告人が勾留されることで、会社の経営が回らず従業員に迷惑を与える」といった事情は保釈の必要性を示す材料になります。
義務的保釈の条件は?
身体拘束を受ける期間が不当に長い場合、「義務的保釈」が認められます。
実務上、一般的に、保釈の多くは、権利保釈か、裁量保釈のどちらかです。
ですが、どちらも認められない場合でも、「義務的保釈」の条件がそろえば、保釈は許可されます。
義務的保釈の条件については、次のような条文があります。
勾留による拘禁が不当に長くなつたときは、裁判所は、第八十八条に規定する者の請求により、又は職権で、決定を以て勾留を取り消し、又は保釈を許さなければならない。
刑事訴訟法 第91条 第1項
身体を拘束されたまま、被告人として刑事裁判を受けることになれば、起訴されてから裁判まで約2か月もの間、被告人勾留が続きます。
その後も、特に継続の必要がある場合は、その身体拘束は1か月ごとに更新され続けることになります。
このとき、身体拘束を受ける勾留が不当に長くなった場合は、裁判所は「義務」として、被告人を保釈して、釈放しなければなりません。

弁護士
不当に長い勾留とは、単なる時間の長さだけによりません。「事件の内容」「犯罪の軽重」「審理の進み具合」「裁判の難易度」など、さまざまな事情から相対的に判断されます。
「不当に長く」にあたる基準となる特定の期間があるというわけではありません。
保釈されるための条件とは?
保釈金保証金(保釈金)とは?
実際に、保釈されるためには、守るべき基本的な条件があります。
まず、保釈の許可が出されても、保釈保証金(これ以降、「保釈金」といいます。)を納付しなければ釈放してもらえません。
保釈を許す決定は、保証金の納付があつた後でなければ、これを執行することができない。
刑事訴訟法 第94条1項
保釈金の納付は、保釈に欠かせない条件となっています。
保釈金は、「被告人の出頭を保証する金額」とされています。
保釈金の相場は、個々の事案にもよりますが、一般の方の場合は150万円~300万円が相場です。
被告人が芸能人や資産家などあれば、もっと高額の保釈金になります。

弁護士
保釈金の金額は、一律ではありません。
「犯罪の性質および情状」「証拠の証明力」「被告人の性格および資産」から、被告人それぞれの情況に応じて、決められます。
また保釈条件に違反せず裁判手続きが終了した場合には、保釈金は返還されます。
保釈の指定条件とは?身元保証人が必要?
保釈が認められるには、保釈されてから判決までのあいだ、守るべき指定条件がかせられます。
指定条件は、被告人の「逃亡や罪証隠滅の防止に必要かつ有効な条件」であるべきとされています。
指定条件は、「被告人の性格」「事件の内容や性質」など、事件ごとに異なります。ですが、多くの事案では、身元引受人(身元保証人)が必要な条件となります。

弁護士
身元引受人は、保釈された被告人の身元を引き受けて、保釈中の生活・行動を監督します。
また、公判期日への出頭を確保する役割も担います。
そのため、同居の家族が身元引受人となることが多いです。
事情によっては勤め先の上司や友人が身元引受人になるケースもあります。
保釈されたあとの条件とは?
無断外泊は、保釈の条件に違反する?
保釈を許可する条件として、保釈中の住居を指定されることがあります。
このような場合、制限住居以外で寝泊まりするなど外泊することは条件違反となります。

弁護士
ただし、裁判所から許可を得れば、保釈中に外泊や旅行が認められることもあります。
被害者への接触禁止は保釈の条件になる?
暴行罪、傷害罪、不同意わいせつ罪(旧 強制わいせつ罪)など他人に被害を与える罪を犯した場合の保釈では、被害者への接触禁止が保釈の条件に入れられることがあります。
被害者と直接会うことはもちろん、電話やメールなど方法を問わず一切の接触が禁じられます。
共犯者同士は接触禁止は保釈の条件になる?
共犯事件の場合、保釈条件に共犯者との接触禁止が付けられることがあります。
保釈中に共犯者と共謀して事件の口裏を合わせたりすることを防止する目的で接触禁止の条件が付けられます。
直接会うだけでなく、電話・メール・SNSなどでも連絡を取ることも禁止されます。
保釈されるための条件に違反したらどうなる?
保釈条件に違反したら身体拘束?
保釈は、保釈の指定条件(外泊禁止・接触禁止など)を守ることを条件に、釈放されることになります。
保釈条件に違反すると保釈が取り消されて、再び刑事施設に収容されることになります。
条件違反の場合については、次のような条文で規定されています。
裁判所は、左の各号の一にあたる場合には、検察官の請求により、又は職権で、決定を以て保釈又は勾留の執行停止を取り消すことができる。
刑事訴訟法 第96条1項
「保釈又は勾留の執行停止を取り消すことができる。 」とあります。

弁護士
保釈の取り消しは、検察官によって請求され、裁判官によって決定されます。
「出頭には必ず応じる」「逃亡をはからない」「罪証隠滅をはからない」「被害者などにお礼参りをしない」「制限住居を守る」といったことを心がけ、保釈の条件に違反しないよう気を付ける必要があります。
保釈条件に違反したら保釈金没取?
保釈条件に違反すれば、保釈金は取り上げられてしまう可能性があります。
保釈を取り消す場合には、裁判所は、決定で保証金の全部又は一部を没取することができる。
刑事訴訟法 第96条2項
保釈された者が、刑の言渡を受けその判決が確定した後、執行のため呼出を受け正当な理由がなく出頭しないとき、又は逃亡したときは、検察官の請求により、決定で保証金の全部又は一部を没取しなければならない。
刑事訴訟法 第96条3項
保釈金は「全部」または「一部」が没取される可能性があります。
保釈金の没取は、裁判官の裁量によって決められます。

弁護士
保釈条件に違反せずに裁判手続きを終えれば保釈金は返ってきます。
しかし保釈金を没取されてしまった場合、その後裁判が終わったとしても没取された保釈金が返ってくることはありません。
保釈の弁護を依頼したい┃弁護士への相談窓口は?
保釈に関するお悩みは、アトム法律事務所にご相談ください。
アトム法律事務所は、刑事事件に注力する弁護士事務所として開設された強みがあります。
ご家族の保釈が認められる可能性はあるのか、どういう条件をクリアすれが保釈の可能性が高まるのかなどのお悩みについて、刑事事件に強い弁護士がお答えします。

弁護士
アトム法律事務所では、警察沙汰になった事件について30分間無料の対面相談を実施しています。
24時間365日、土日や深夜でも繋がる相談予約窓口にいますぐお電話ください。
 刑事事件でお困りの方へ
刑事事件でお困りの方へ
ご希望される方はこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了


弁護士
具体的には「殺人罪」「強盗致死傷罪」「現住建築物等放火罪」などの罪です。
このような、いわゆる重大犯罪に該当しない罪であることが、保釈の一つ目の事由となります。