
第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件弁護士アトム」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。
アトムは夜間土日も受け付けの相談窓口で刑事事件のお悩みにスピーディーに対応いたします。
自転車窃盗は逮捕される?逮捕後の流れ・刑罰・前科はどうなる?
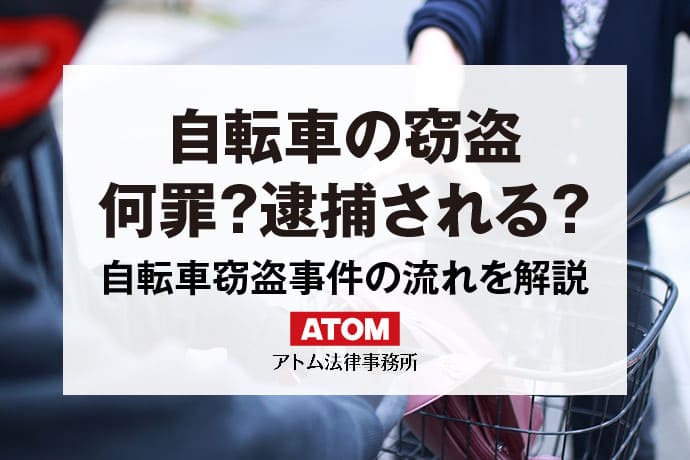
- 自転車窃盗は逮捕される?可能性は?
- 自転車窃盗は何罪?刑罰は?
- 自転車窃盗の逮捕の流れは?時効は?
- 自転車窃盗の前科をつけたくない。回避するには?
- 自転車窃盗をした未成年。刑罰や学校はどうなる?
この記事では、自転車窃盗の逮捕、刑罰、刑事手続きの流れなどについて不安をお持ちの方を対象として、上記のような疑問にお答えしています。
つい出来心で駐輪していた自転車を盗難してしまったり、過去に自転車を盗難したことがありまだ時効を迎えていない状態であったりなど、「自転車盗難が罪になる」という意識が薄いまま犯行に及び不安を抱えている方もいるのではないでしょうか。
自転車窃盗は犯罪です。よって、捜査機関に自転車を盗んだことがバレれば、逮捕につながることもあるでしょう。
ぜひ最後までご覧ください。
 刑事事件でお困りの方へ
刑事事件でお困りの方へ
ご希望される方はこちら
目次
自転車窃盗の逮捕の可能性は?
逮捕の可能性は?
被害者から自転車盗難の被害が出されても、検挙率は決して高くないのが現状です。
しかし、自転車窃盗でも逮捕される可能性はあります。
警察官がたまたま張り込みや待ち伏せををしていた場合、現行犯として逮捕されるケースもあるでしょう。
もっとも、逮捕されるかどうかは、個別の事案しだいです。
ご自身の事案において、自転車窃盗の証拠があるかどうか等に左右されます。確率論では、逮捕の可能性が分からないというのが実情です。
ご自身のケースで逮捕される可能性があるのかどうか、その後の対応はどうすればいいのかについては、弁護士に早期にご相談されることをおすすめします。
逮捕のきっかけは?
逮捕には大きく「現行犯逮捕」と「通常逮捕」があります。

現行犯逮捕は、通りがかりの人でもできるため、私人逮捕とも呼ばれています。
自転車盗が現行犯だった場合は、一般人による逮捕が認められているといえるでしょう。
通常逮捕となるケースは、たとえば被害者から盗難届が出されていた場合です。
防犯カメラなど証拠が残っていれば、後日逮捕される可能性はあるでしょう。
また、パトロール中の警察官が職務質問を行い、自転車について照会をして盗難車であることが判明し、その場で逮捕されるといったケースもあります。
自転車窃盗の時効は何年?
刑事事件の時効(公訴時効)とは?
自転車窃盗の時効は7年です。
この時効は、公訴時効と呼ばれるものです。
公訴時効を過ぎると、自転車窃盗の犯人として起訴されることはないですし、その前段階として逮捕されることもありません。
逆にいえば、自転車窃盗をしてから7年間は、逮捕される可能性があるということになります。
民事事件の時効とは?
なお、7年を経過したとしても、民事事件として損害賠償責任を問われる可能性もあります。
公訴時効は刑事事件の時効であって、民事事件の損害賠償責任は、刑事事件とはまた別物です。
自転車の持ち主が損害賠償請求を視野に入れている場合、時効が完成すれば損害賠償請求権は消滅、裏を返せば、時効が完成するまでは損害賠償の請求をされる可能性があります。
民事事件として賠償請求される可能性のある期間は、被害者が犯人を知ったときから3年、または自転車窃盗をした時(≒不法行為の時)から20年になります。
公訴時効と民事の時効の違いは?
刑事事件の公訴時効と、民事上の時効の違いについては、以下のように整理できます。
| 時効の種類 | 年数 |
| 公訴時効 (起訴されなくなる時効) | 自転車窃取から7年 |
| 民事上の時効 (不法行為責任の時効) | 加害者を知ったときから3年(知らない場合は20年) |
刑事事件で捜査を受けた場合、刑事事件をおこしたことで被害者に与えた損害について、損害賠償の問題も浮上することがあります。
弁護士に刑事弁護を依頼すると、被害者の方との示談交渉をおこなってくれる場合があります。そのため、刑事弁護を依頼したら、結果として、刑事事件だけでなく、民事の賠償問題についても一緒に解決できることもあるでしょう。
自転車窃盗の刑罰は?
自転車窃盗は窃盗罪?
自転車窃盗は、他人の自転車を盗む犯罪です。
自転車窃盗は、基本的には、窃盗罪になります。
つい軽はずみな行動であっても他人の自転車を盗んでしまった場合、「窃盗罪」として処罰されます。
「乗り捨てたから、今は手元にない。」という場合でも、窃盗罪として処罰されます。

弁護士
窃盗罪は、財産罪の中でも「領得罪」にあたります。
自転車の盗難で窃盗罪に該当するかどうかは、「占有の移転」があったか無かったかが判断のポイントになってきます。
被害者の意思に反して、自転車を持ち去ったのであれば、所持の有無にかかわらず、「窃盗罪」として処罰される可能性があるでしょう。
窃盗罪の刑罰は?
窃盗罪の刑罰は、「10年以下の懲役」または「50万円以下の罰金」です。
(窃盗)第二百三十五条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
刑法235条
自転車窃盗になるかどうか微妙なケースとは?
たとえば、「友人所有の自転車を、友人に黙って借りた」というケースではどうでしょうか。
窃盗は、物の所有者を無視して、自分の物にしてしまおうという意図(不法領得の意思)をもって、他人の物をとったときに成立します。
不法領得の意思
窃盗罪が成立するには、不法領得の意思があることが要件となっています。
不法領得の意思とは、「権利者を排除し、他人の物を自己の所有物とするというような意思」のことをいいます。
自転車の持ち主に返還する意思があり、実際に使用後すぐに返却した場合は、窃盗罪にならない可能性が高いでしょう。
一方、いくら返還する意思があったと言っても、何時間も何日間も借りっぱなしだったのであれば、客観的にみて不法領得の意思があるとされ、窃盗罪になると判断される可能性が高いでしょう。
ご自身の事案が自転車窃盗として罰せられるのかどうかについては、個別の事情によります。「犯罪にならないと思っていたら警察沙汰になってしまった」といったケースは数多くあります。
まずは早めに弁護士に相談して不安を解消しておくのがよいでしょう。
自転車窃盗の不法領得の意思って?
自転車を盗んでしまった場合は、「『不法領得の意思』をもって、他人の財物の占有を自己の占有に移した」といえる場合に、窃盗罪が成立します。
不法領得の意思とは、自分の物にしたいと思う意思のことです。

弁護士
判例上、不法領得の意思は「権利者を排除し、他人の物を自己の所有物としてその経済的用法に従いこれを利用処分する意思」と定義されています。
不法領得の意思があれば窃盗罪になります。一方、不法領得の意思がなければ、単に使用しただけで、窃盗罪にはなりません。
実務上、長時間の使用、高価な乗り物の使用などは不法領得の意思が認められやすい傾向があります。窃盗罪であるとの認定が下される可能性が高いでしょう。
自転車窃盗が窃盗罪「以外」になる場合は?
施錠されている自転車を窃盗しようとしたら?
施錠されている自転車を窃盗した場合、器物損壊罪に当たる可能性もあります。
(器物損壊等)第二百六十一条
前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
刑法261条
施錠されている自転車の場合、そのまま自転車を運転することはできず、鍵の部分や、自転車周辺に施されたチェーンを破壊することもあるでしょう。
このような破壊行為は、「器物損壊罪」にも該当します。窃盗とは別に、器物損壊罪で再逮捕される可能性もあります。
自転車窃盗の目的で住居の敷地に侵入したら?
自転車窃盗の目的で、他人の住居やその周辺をまたぐケースもあるでしょう。
住居等への不法侵入をともなう場合、住居侵入罪、建造物侵入罪として処罰される可能性もあります。
(住居侵入等)第百三十条
刑法130条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
自転車窃盗で逮捕された後どうなる?
自転車窃盗で逮捕後の流れは?勾留とは?
自転車窃盗で逮捕された場合、まずは、警察から取り調べを受けます。
警察の取り調べの時間は、法律で48時間となっています。
その後、釈放されなければ、検察官に事件が送られて(検察官送致)、今度は検察で取り調べを受けることになります。
検察へ送られたあとは、検察官の判断により、さらに身柄拘束が続くことが予想されます。
検察官のもとで身体を拘束されることを「勾留」といいます。
勾留される期間は、最大20日間です。
そのため、逮捕後、ずっと釈放されなければ、最長23日間、身柄を拘束され続けることになります。

逮捕・勾留中の釈放を目指すのであれば、弁護士に、警察署内の留置場に接見に来てもらって、釈放を求める弁護活動をしてもらう必要があります。
身体拘束のリスクに対応するには、弁護士への早期相談がベストです。
未成年の自転車窃盗はどうなる?
未成年者の場合、逮捕・勾留までの流れは、成人と同じです。
しかし、その後の流れは違います。
成人の刑事事件の手続きとは区別されています。未成年者の刑事事件は「少年事件」と呼ばれますが、少年事件はまずは家庭裁判所に送致されるというのが一般的です(全件送致主義)。
少年事件は、少年法にしたがって手続きが進みます。
14歳未満の場合、刑事責任を負わないとされています。
ただし、事件の内容にしたがって、その後の処分内容が変わったり、児童相談所に事件が送られたり、学校への連絡などの問題もあったりします。
そのため、少年事件では、弁護士が付添人として関与することが一般的です。
自転車窃盗をしたら学校はどうなる?
身体拘束が長期に及ぶと、毎日の授業や、進学に影響が出る可能性は高いです。
学校への調査が入ることもあります。
自転車窃盗の事実や逮捕された事情等について、学校が知られてしまうと、事案によっては、学校を停学になる、退学になるといったケースも予想できます。
こういう場合、弁護士は、捜査機関や家庭裁判所に対して、「学校には連絡をしないでほしい」というような申し入れをおこなってくれます。
弁護士の申し入れによって、必ず学校に連絡がいかないとまでは断言できません。ですが、弁護士は、少年事件の付添人として法的な観点から、かつ第三者としての視点から、申し入れてくれます。
そのため、自分でお願いするよりも、実効性があるといえるでしょう。
逮捕・勾留されたら仕事はどうなる?
逮捕・勾留中は基本的に外部と連絡ができないため、会社員の方であれば、無断欠勤が続くことも予想されます。
そのような場合は、弁護士に依頼すれば、弁護士から勤務先に連絡を入れてくれるでしょう。
また、弁護士面会(接見)の際、ご家族への伝言を頼むことで、ご家族経由で勤務先に連絡を入れるという方法も考えられます。
自転車窃盗で前科はつく?悪質な場合や再犯の場合は前科?
有罪判決がだされれば、前科がつきます。
自転車の窃盗の場合、とくに初犯であれば、検察官に送致されず、「微罪処分」にとどまることもあるでしょう。
微罪処分であれば、前科はつきません。
しかし、検察官に送致されることもありますし、再犯だったり、行為態様が悪質だったりした場合には、逮捕・勾留後、起訴されるケースもあるでしょう。

弁護士
窃盗罪の刑罰は、懲役と罰金です。
罰金刑は、刑務所に収監されることはありません。
でも、罰金刑も、有罪判決のひとつです。つまり、罰金刑でも前科はつくのです。
自転車窃盗で逮捕・起訴されないためには?
自転車窃盗の示談とは?
自転車窃盗で逮捕・起訴を回避するには、被害者との「示談成立」が重要です。
示談とは、民事上の責任を当事者の話し合いによって解決する手続きのことです。
加害者から被害者に対して、謝罪を申し入れ示談金を支払い、民事上の責任を解消します。そして、示談書を締結します。

示談書には、被害者の方の「加害者の厳罰を望まない」「刑事告訴を取り下げる」「犯人を許す」といった文言を盛り込むことも多いです。
示談の締結そのものも重要ですが、このような宥恕(ゆうじょ)の文言を入れることができると、起訴を回避できる可能性が高まります。不起訴になれば、前科はつきません。
また、もし起訴されてしまった場合でも、刑罰が軽くなるといった影響も考えられます。
被害者の意思が記載された「示談書」を捜査機関に提出することは、刑事事件の解決にとって、非常に有効なのです。
ただし、示談を、自分で進めていくというのはかなり難しいのが実情です。多くの場合、弁護士に代わりに示談をしてもらう方が多いでしょう。
というのも、刑事事件の被害者の方は、加害者本人と直接連絡を取ることに抵抗があります。性能の良い電動自転車やロードバイクなどであれば、被害感情も大きくなると予想されます。
そもそも、自転車窃盗の場合、どこの誰とも知らない方の自転車を盗んでしまったということも多いので、被害者の方の連絡先を知らないということも多いでしょう。
そのため、示談交渉をするには、その前提として、まずは捜査機関から被害者の連絡先を教えてもらうことが必要になります。
ですが、実務では、加害者本人には、被害者の連絡先を教えてもらえないことが多いものです。警察や検察から「情報を弁護士限りにとどめておくのであれば、弁護士に被害者の連絡先を教られる」と言われることがよくあります。
この場合、もしも弁護士がついていないと、示談交渉を開始することすらできない事態になります。

示談では、被害者の方に対して、被害感情の有無、被害弁償の必要性、いくら慰謝料や示談金が必要なのかといった希望金額を聴取することも必須です。
このような事項をご自身で聴取し、交渉していくのは難しいものです。第三者である弁護士を間に入れることで、スムーズに示談交渉を進めることが期待できます。
自転車窃盗の悩みを弁護士に相談したいときは?
今すぐ相談予約できる窓口は?
自転車窃盗について、今後の流れについて相談するためにも、示談をスムーズに進めるためにも、重要なことがあります。それは、刑事事件の解決実績が豊富な弁護士のバックアップを受けることです。
アトム法律事務所は、刑事事件に注力する弁護士事務所として発足しました。
設立当初から刑事事件の解決実績があり、実績豊富な弁護士事務所です。
自転車窃盗の示談交渉、不起訴のための弁護活動など刑事手続き全般について、全面的なバックアップを目指しています。
アトム法律事務所では、刑事事件でお悩みについて早期の事件解決を目指すために、24時間365日、夜間、土日も相談受付のできる窓口を設置しています。
早期の対応が、その後の流れに影響します。ご予約お待ちしています。
 刑事事件でお困りの方へ
刑事事件でお困りの方へ
ご希望される方はこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了


弁護士
窃盗犯である自転車盗の時効の起算点は、自転車を窃取したときです。
犯罪行為が終わった時点からカウントすることになっています。