
第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件弁護士アトム」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。
アトムは夜間土日も受け付けの相談窓口で刑事事件のお悩みにスピーディーに対応いたします。
万引き事件の弁護士費用は?示談は弁護士に相談すべき?示談できない場合の対処法は?
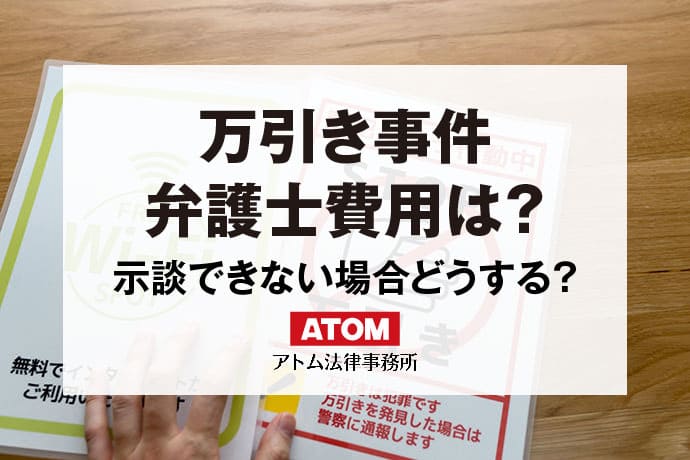
- 万引き事件の弁護士費用は?
- 示談できない場合の対処法は?
- 被害弁償と示談は違う?
万引きをしてしまい、今後の刑事処分を心配されている方は多いと思います。
万引き事件は、被害者との示談が重要です。しかし被害者と示談をしたいと思っても、店舗の方針や相手の被害感情が強い場合は、示談に応じてもらえないこともあります。
示談に応じてもらえないまま何もせずにいると、起訴されてしまう可能性が高まります。
今回の記事では、万引き事件を弁護士に依頼する際の費用や示談の効果、示談できない場合の対処法を詳しくご紹介します。
 刑事事件でお困りの方へ
刑事事件でお困りの方へ
ご希望される方はこちら
万引き事件の弁護士費用は?
万引き事件の弁護士費用はいくらかかる?
万引き事件の弁護士費用は事務所によりますが、逮捕の有無、被害者の人数などによって左右されるのが一般的です。
弁護士費用は事務所のホームページに記載されていることが多いので、確認してみてもいいでしょう。
また、弁護士を選ぶ際には、費用のみならず弁護士の人柄、万引き事件の解決実績などを参考にすることがおすすめです。
関連項目
・弁護士費用┃弁護士法人 アトム法律事務所┃逮捕勾留中の事件など
万引き事件の示談交渉を弁護士に依頼するためには?
万引き事件の示談交渉を弁護士に依頼するためには、弁護士と委任契約を結ぶ必要があります。
契約を結んだ弁護士は、依頼者の代理人として、示談交渉を一括して引き受けることが可能です。
依頼された弁護士は、被害者が複数いた場合でも、各被害者と示談交渉を行います。

弁護士
一般的には、刑事事件の弁護活動は示談交渉だけでなく、捜査機関や裁判所への対応を含めて一括で行うものです。
示談の費用だけでなく、公的機関への対応も含めて、トータルの費用がいくらになるかが肝心です。
被害者に支払う示談金と、弁護士に支払う弁護士費用は別になるので注意してください。
万引きで被害届が出されたら示談するべき?被害弁償と示談は違う?
万引き事件での示談の効果は?

万引き事件で被害者と示談する一番の効果は、不起訴処分・微罪処分の可能性を高めることです。
事件の起訴・不起訴を判断する検察官は、処分の判断にあたり、事件の態様や被害者の処罰感情を考慮します。
示談によって当事者間の問題は解決していると示すことができれば、被害者の処罰感情も低いと判断され、不起訴の可能性が高まるのです。
また、通常警察が認知した事件は検察に送致されますが、万引き事件は例外的に、微罪処分という手続きで事件が終了する場合があります。
微罪処分になれば、検察に事件が送られず、起訴・不起訴の判断を受けないため、前科はつきません。

弁護士
何を「微罪」にするかは検察官が決めています。
万引き事件の場合は、被害金額が少なく、被害回復がおこなわれていること、今後再犯の可能性がきわめて少ないことなどが微罪処分の条件として挙げられます。
関連項目
・万引きで起訴されるのはどんなとき?初犯でも起訴される?再犯の場合は?
万引きで被害届が出されたら示談するべき?
万引きで被害届が提出されると、警察による捜査が開始されるきっかけになります。
万引きで被害届が提出された場合は、起訴・不起訴の判断が下る前、つまり捜査段階で示談を成立させることが重要です。
早期に示談を成立させることができれば、逮捕の回避や、不起訴の可能性を高めることができます。
起訴されてしまうと99.9%の確率で有罪になり、前科がついてしまいます。
前科を避けたいと考える方は弁護士に相談しましょう。

弁護士
前科は一度ついてしまうと一生消えることがありません。
前科がつくと、就職活動や海外渡航などで不利益を被る可能性があります。
関連項目
・窃盗・万引きでは逮捕されない?現行犯以外で捕まるきっかけや逮捕後の流れ
万引きの被害弁償とはどういうもの?
万引きをしてしまった場合には示談が重要ですが、被害者が必ずしも示談に応じてくれるとは限りません。
万引き事件の加害者が取るべき手段として、示談のほかに被害弁償というものがあります。
被害弁償とは、窃取した商品の被害金額の返済、その他金銭などの賠償をいいます。
お店の商品を万引きしたのであれば、被害品である商品そのものの返却はもちろん、場合によっては該当商品における損害賠償をしなければなりません。
たとえば、すでに使用してしまったものや、窃取したことにより使い物にならなくなった商品は、商品代金額相当額も請求されることが多いです。
また、被害弁償の中に窃盗事件による迷惑料などが計上されることも考えられます。

弁護士
被害弁償を行うことも、刑事処分に対して一定の効果を得られる場合があります。
被害弁償で被害回復を図ることで、軽微な事件であれば微罪処分の獲得や、逮捕を回避できる可能性が高まります。
万引きの被害弁償と示談は何が違う?
万引きにおける被害弁償は単に被害回復を図るために行われるものであるのに対し、示談は民事上の解決を双方が合意している点で違いがあります。
示談は、当事者間の話し合いによって事件を解決する民事上の手続きです。
示談が成立している場合は、被害回復がなされ、当事者間の問題は解決したと判断される可能性が高いです。
一方で被害弁償だけで示談ができていない場合は、被害者に処罰感情が残っていると捜査機関などに判断される可能性があります。

弁護士
示談がかなわなくとも、被害金の弁償だけでも尽くすことは重要です。
弁護士は被害金額自体を受け取ってもらえない場合、たとえば被害額の一部だけでも支払えるよう交渉することもあります。
万引きで示談ができないときの対処法は?万引きの刑罰は?
万引きで示談ができないときの対処法は?
万引きで示談ができない場合の対処法は、以下のものがあります。
示談できないときの対処法
- 現金書留で送付する
- 供託する
- 贖罪寄付する
- 示談交渉の経過がわかる報告書を作成する
それぞれ詳しく解説していきます。
現金書留で送付する
万引きで示談はおろか、被害弁償すら受け取ってもらえないケースは、現金書留で被害賠償を送付し、受領の手立てを取ることがあります。
被害賠償を受け取ってもらえないほどの被害回復が難しい場合でも、できる範囲で被害回復の姿勢を示すことは重要です。
示談に応じてもらえないからといって、被害回復もしないと警察や検察などの捜査機関に反省の意思がないと判断され、起訴される可能性が高まってしまいます。
もし、送付した金銭を受領してもらえた場合は、現金書留の控えなどを証拠として残しておく必要があります。
供託する
被害感情が強く、示談に応じてもらえない場合は、刑事責任を軽減するために供託という方法を取ることがあります。
供託とは、金銭を供託所に預け、被害者が被害弁償額をいつでも受け取ることができるようにするものです。
事件直後は被害感情が強い場合でも、事件から一定期間時間が経過したときには賠償金を受け取ってもらえる可能性があります。
被害者と示談をしたことにはなりませんが、被害者がいつでも受け取れる金銭を用意し、被害回復を図ったという反省と謝罪の意思を示すことができます。
贖罪寄付する
被害者と示談ができなければ、贖罪寄付をするという手段も有効です。
贖罪寄付とは、刑事事件の加害者が反省や謝罪の気持ちを示すために行う寄付のことを言います。
被害者と示談ができない場合や、被害者のいない事件が対象となり、弁護士会や慈善団体に寄付金を納付します。
贖罪寄付の納付は、各地の弁護士会にて手続きを行います。
納付の金額は示談金の相場が目安になることが多いです。
万引き事件の示談金の相場はおおよそ30万円前後であるため、それと同等の金額もしくは少なめの金額になるでしょう。
納付が完了すると、「贖罪寄付を受けたことの証明書」を受け取れます。
それをもって被疑者や被告人の反省に代えた主張をおこなうことが可能です。
示談交渉の経過がわかる報告書を作成する
被害者から法外な示談金を要求された場合などは、示談交渉の経過がわかる報告書を作成することもあります。
謝罪の意思を示し、相場の金額で示談を試みた、という報告書を残しておくことが必要です。
実際に示談が成立していなくても、捜査機関も被害回復の意思があるとみなし、一定の考慮はしてくれるでしょう。
弁護士は、示談交渉が進まない場合には報告書などと題して、警察官などの捜査機関に資料として提出することもあります。

弁護士
一概に示談できないといっても、どの方法を取るか、示談交渉をどこまで粘り強く続けていくかなどは、一度示談交渉の経験が豊富な弁護士に相談することをおすすめします。
事件内容・被害者の特質などにより、取るべき対処法が異なることは念頭に置いておきましょう。
弁護士に相談するのが早ければ早いほど、その後に取れる弁護士の対応の幅が広がります。
万引きはどんな刑罰を受ける可能性がある?
万引きは一般的に窃盗罪に該当する犯罪行為です。
窃盗罪の法定刑は「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」です。
スーパーやコンビニなどでの万引き行為は、窃盗罪の典型例といえるでしょう。
万引きの金額や量にかかわらず、万引き事件を起こしてしまった場合は定められた法定刑の範囲で刑罰が科されます。
原則として懲役刑は1か月以上、罰金刑は1万円以下です。

弁護士
刑罰の量刑は、事件の態様や、示談の有無、被害回復を行っているかどうかなどから総合的に判断されます。
被害金額が高額の場合や、繰り返し犯行を行うなどの悪質な場合は、量刑が引き上げられる傾向にあります。
関連項目
万引き事件の示談でお悩みの方は弁護士に相談?
万引き事件で示談ができないと前科がついてしまう?
万引き事件で示談ができなくても、ご紹介した供託や贖罪寄付などの対処法を行うことによって、前科を付けずに事件を解決できる可能性はあります。
しかし、反省と謝罪の意思を示したとしても、何回も万引きを繰り返している場合や、事件の態様が悪質と判断されてしまった場合は起訴され、有罪判決になることもあります。

弁護士
万引きは初犯であれば、起訴されない可能性も高いです。
ただし、計画的な犯行や、万引きの被害が大きい場合などは起訴される可能性もあります。
弁護士であれば示談交渉できる可能性がある?
もし店舗の方針などではなく、被害者の被害感情が強いために示談が難しい場合は、弁護士が示談交渉をすることで示談に応じてもらえる可能性があります。
むしろ、示談交渉には弁護士の依頼が事実上必須になります。
被害者は加害者との直接のやり取りを嫌がるケースが多いからです。
弁護士を依頼した場合の示談交渉は、基本的に弁護士と被害者側で行います。
加害者との直接のやりとりを嫌がる場合でも、弁護士を通してであれば示談交渉に応じてくれる可能性はあります。
また、示談交渉の経験が豊富な弁護士であれば、被害者の心情に寄り添いながら、適切な金額とタイミングで示談交渉を行うことができるでしょう。

弁護士
もっとも、被害者の被害感情や店舗の方針によっては、弁護士が介入しても拒否される可能性も否めません。
そのような時も、ある程度時間を置いたり、アプローチ方法を変えたりしていくなど、最大限示談ができるように活動していきます。
万引き事件に強い弁護士の相談窓口は?
万引き事件で被害者と示談を行いたいと考えている方は刑事事件に強い弁護士に相談しましょう。
アトム法律事務所は刑事事件専門の弁護士として沿革した実績があり、これまでも万引き事件の豊富な解決実績があります。

弁護士
アトム法律事務所では警察が介入した事件について初回30分無料の対面相談を実施しています。
24時間365日繋がる無料相談予約窓口にいますぐお電話ください。

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了


弁護士
弁護士費用は事件の態様によっても大きく変動するので、まずは初回の弁護士相談で費用の見積もりをしてもらうのが良いでしょう。
アトム法律事務所では、警察が介入した事件に関して、初回30分間無料の対面相談を実施しています。